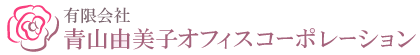認知症観を変える大事なこと

🌲
昨日は、午前中10月18日の研修打ち合わせがあり、
その後、引き続き東京センターの永田久美子先生の
学びの時間を得ることができました。
🌲
認定看護師さんと、ご家族だけの限定されたものでしたが、
今年は認知症基本法の元年でもあり、
また、どの地方においても高齢化率が高くなり市町村等の小さな地区においては
高齢化率40%を超えるような地域もあり、また人口減から特養なども空きの状況が増すように
なってきているようです。
認知症の高齢者および軽度認知障害の高齢者の推計値(2024年5月8日 内閣府)
には、軽度認知障害の高齢者も入るようになり、今での統計をかなり増す状況になっています。
🌷
今後、認知症になってもお一人で暮らす方が多くなるのが当然の時代となり、
まちづくりも、経済においても大きな変わりどころで変革期であるようです。
早期に挑戦をされた商工会や、町内会、学校等、認知症の人が地域で過ごすことが
「普通」として暮らしを整えることが急務と感じました。
🌲
介護現場の在り方も地域のとらえ方も今までの病気目線で見るのではなく、
人は、誰もが一人の人として個性をもって暮らしており、
それは、認知症の人も同じで個別の生き方があり希望があり、
認知症と診断された場面では、戸惑いや苦しみを持たれた人も居るかと思いますが、
本人がそのような状況から生み出した小さな希望が叶うことで、
認知症の人にとっては大きな力となり、その地で再び暮らし続けることができます。
🌲
ピアサポートでは、認知症と診断を受けた人が認知症の人の相談にも乗っています。
そのような環境は、とても心が安定し落ち込むことも減少し安心する状態になるのかと思います。
学びの病気の理解から病気1本のアルツハイマー等、
病気の視点で見ることではなくその人、独自の個別を見る視線が必要となり
認知症の人への見方も大きく変化することが求められています。
🌲
認知症は、怖い病気という間違った認知症観から、
否定をするようになると、地域で暮らすことが困難となります。
🌲
『すごいね!認知症という病気になっても旅行も行けるし、
皆さんにお話しも組み立てて話すことができるし、
国の対策会議でも、(何日も前から何度も読んだり書いたり、考えたりするけれど、)
意見を伝えられるそのような力があるんだね!」と。
個別の考え方をしていただくと、
それまで認知症の人が力を注いできた、
大工仕事でも、お料理でも、野菜つくりでも
(間違ったと気づいた人は、責めずに黒子となり手助けをする)
環境を変えずに地域で暮らすことで、その力を持ち続けることができますね。
🌷
誰もが成り得る認知症ですから、
誰もが地域で暮らしていけるように一つ一つ整えるのが地域力で、
それが後の自分の為になるのですね。
🌲
みんな笑顔で地域で暮らし続ける世界が整うことが、
弱くなったときに最後に求める希望なのかなと思います。